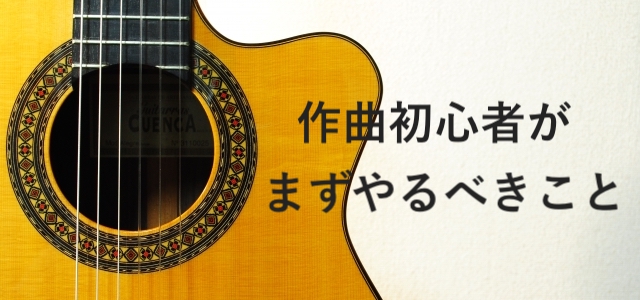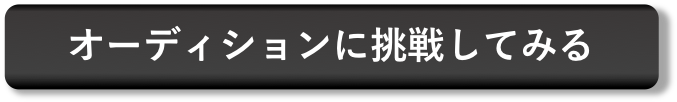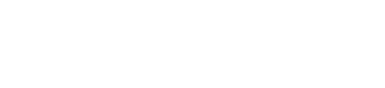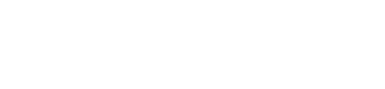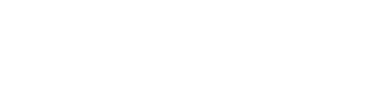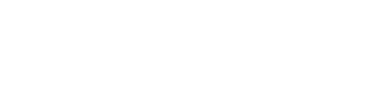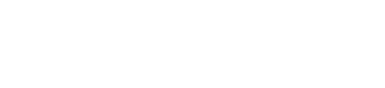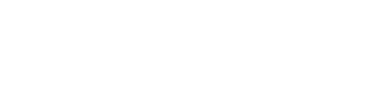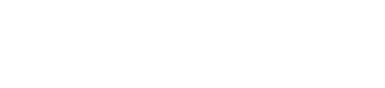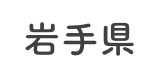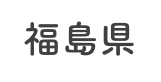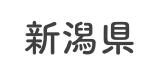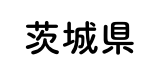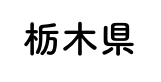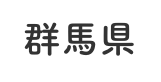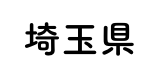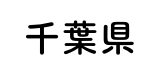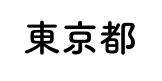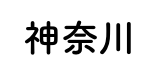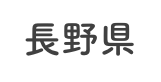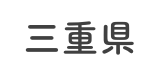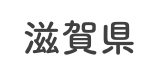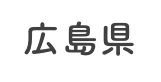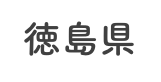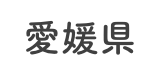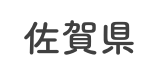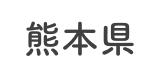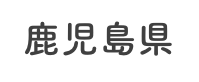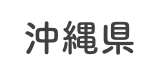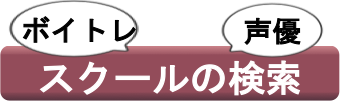あの歌手のような曲を作ってみたいと思ったことはありませんか?
音楽理論などを知らないと無理だと考える人は多いでしょう。
しかし、ポイントを抑えておけば、誰でも曲を作ることはできます。
そこで今回は、初めて手がける方でも簡単に作曲ができるコツを紹介します。
目次
作曲する時にすべきこと

作曲する時の作業の要素とやり方ついて、実体験をもとに説明します。
何点かありますが、順序にはこだわらずにどれから始めてもよいと思います。
例えば、海外ではリズムから作る方も多いようですが、日本ではコード進行やメロディから作る方が多いように思います。しかし、どちらも間違いではありません!
リズムやテンポを考える
曲全体のテンポやリズムなどを決めて構想を考えます。
明るいイメージで速いテンポや、スローなバラードなど曲のイメージをふくらませてください。次に曲全体のリズムを決めます。
4拍子の8ビートや16ビート、ボサノバなどのラテン調、8分の6拍子で流れるような雰囲気を出すなど、自分の好きなリズムを考えましょう。
日本語の歌詞をつける場合、最初は4拍子が適していると思います。
曲の構成を考える
- イントロ
- Aメロ
- Bメロ
- (Cメロ)
- サビ
- 間奏
- アウトロ
上記は基本的な曲の構成です。もちろん、他の構成でも問題ありません。
曲の構想は、大小のブロックで考え、始めは大きなブロックから着手するとよいでしょう。例えば、サビから、イントロから始めるといった感じです。
ちなみに、Aメロ(導入)Bメロ(サビにつなげる)サビ(盛り上がり)の小ブロック構成になります。間奏やイントロ、エンディングは、曲の始まりから終わりまでの全体の構成をまとめるブロックです。
コード進行とメロディ

コードを聴くと、メロディが自然に浮かんできます。いろんなコードを聴きながら口ずさんで自然に出てくる感覚を味わってみましょう。コード進行をもとにメロディを作り出すことにつながります。
現在使われている代表的なコード進行は、今まで多くのミュージシャンが使ってきたものがまとまったものといえます。既存の曲のコード進行に、他のコードを加えたり入れ替えたりしてみると理解が深まります。
代表的なコード進行を紹介します。
基準になるコードをⅠと表現します。例えば4度上のコードを進行上でⅣ5度上はⅤです。基準はCとAmで統一しました。
基本のスリーコード
Ⅰ、Ⅳ、Ⅴのスリーコードから構成され、あらゆるコード進行の基本になります。
|C(Ⅰ) |C(Ⅰ) |F(Ⅳ) |G(Ⅴ) |
オーソドックスな循環コード
何度も繰り返すことができる進行を循環コードと呼びます。基本のスリーコードにⅥmを加えます。
|C(Ⅰ) |Am(Ⅵm)|F(Ⅳ) |G(Ⅴ) |
イチロクニーゴー
もっとも有名な循環コード。進行のローマ数字を続けて読んだ名称です。
|C(Ⅰ) |Am(Ⅵm)|Dm(Ⅱm)|G7(Ⅴ7) |
有名曲でよく使われるコードパターン
ビートルズの「レット・イット・ビー」など、有名な楽曲でよく使われるコード進行です。
|C(Ⅰ) |G(Ⅴ) |Am(Ⅵm) |F(Ⅳ) |
マイナーの基本のスリーコード
マイナーの基本のスリーコードです。
|Am(Ⅰm)|Dm(Ⅳm)|Em(Ⅴm)|Am(Ⅰm)|
マイナー循環進行
代表的なマイナーの循環パターンです。
|Am(Ⅰm)|F(♭Ⅵ) |G(♭Ⅶ) |C(♭Ⅲ) |
ことばのリズムとメロディ

歌を作る方法は大きく分けると2つあります。
歌詞が先にあってメロディを後からつけていく「詞先(しせん)」と、メロディに歌詞を当てはめていく「曲先(きょくせん)」です。より自由でバラエティに富んだ曲つくりには曲先(きょくせん)が良いのですが、今回はわかりやすい詞先(しせん)に重点を置きます。
日本の話しことばとリズム
インスピレーションだけでメロディを作るのは難しいので、話しことばに潜んでいるリズムと音階をモチーフにしてメロディを作ってみましょう。
日本の話ことばは、4拍子の繰り返しといわれています。
日本人が感じる安定した話しことばは、4拍子の文節の中で、複数の音符と間を埋める休符で構成されているのです。
例えば、音符をタン(4分音符)やタタ(8分音符)、休符をウン(4分休符)で表してことばに重ねてみると以下のようになります。
|わたしは(休)(休) |あなたのことが |すきなの(休)(休)
タタタタ ウン ウン タタタタタタタン タタタタ ウン ウン
すべての文節が4拍子で、曲の小節に置き換えると、ことばのリズムの基本形ができます。音符を長くしたり短くしたりすれば、オリジナルのリズムを作ることも可能。他のことばを当てはめて、倍の2小節にしたり、前の小節の最後の音から始めたり工夫をしてみてください。
ことばに潜む音階を聴き取る
リズムができると次はメロディです。ことばには自然に音階もついています。普段の会話では気にはなりませんが、話す時の抑揚や感情もメロディにつながるのです。
声を出して上の文章を読んでみると音に高低がついているのが感じられるでしょう。わかりやすくするために、例文のことばに高中低で音の高低をつけてみました。
|わたしは(休)(休) |あなたのことが |すきなの(休)(休)
低中中中 中高中低低中低 中高中低
上記のように、話す時にできている音程を上下させながら、小節に音階をつけていくとメロディになってきます。今回紹介したのは、話すことばの音程からメロディをつけていく簡単な方法です。自由な発想で試してみてください。
曲先(きょくせん)で歌を作る場合も、最初にリズムを考えるとイメージがわいてきます。
イントロ、アウトロ、リフの導入

歌部分のブロックができあがったら、曲の構成に合わせたアレンジに入りましょう。イントロ、間奏、エンディングなどを決めていきます。
イントロ(イントロジュースの略:前奏)
曲の印象を左右する重要なブロックで、歌のブロックをすべて作った後に作曲するとイメージがわきやすいようです。曲中でまったく使われていないメロディにすることもあれば、サビやAメロをイントロに採用したりする場合もあります。
間奏(ソロ:歌とブロックの間にソロパートを入れる)
間奏が入ることによって、曲全体に立体感が出て、構成もはっきりします。AメロやBメロ、サビのいずれかのコード進行を使って、楽器パートのソロを入れるのが一般的です。
アウトロ(エンディング:音楽造語で楽譜には記載されない。海外ではエンディングと呼ぶ)
曲の最後のシメの部分です。余韻を残した終わり方を心がけましょう。イントロ部分をエンディングに採用したり、サビを繰り返したりする手法が一般的に用いられます。
リフ(リフレイン:繰り返しの意味)
コードの構成音で作るパターンをくり返すのが一般的で、曲全体のリズムを決めた時の1小節のリズムパターンに、力強いメロディをのせて作ります。使われるのはロック調の曲などです。
曲中におけるフレーズのアレンジについて

それぞれのブロックでメロディができあがったら、曲の抑揚やメリハリを表現するためのフレーズアレンジを加えましょう。簡単な2種類のアレンジについて解説します。
4小節の最後に奏法やリズムを変える
現存する曲のメロディ構成は4小節または8小節でワンセットです。
アレンジを加えるのは4小節目か8小節目。各小節のリズムまたは伴奏の音を変化させます。よく使われるのは、フィールインという短いソロパートを入れる方法で、最後の2拍程度に導入される曲が多いようです。
奏法や音、リズムの変化で曲のメリハリをつける効果が期待できますが、フィールインばかりが目立ってしまうと主題のメロディが隠れてしまうので気をつけましょう。
歌の1番と2番で変化をつける
歌の1番と2番は、同じ演奏の繰り返しになることがほとんどですが、ただの繰り返しでは、せっかくの曲が平坦で抑揚がないものになってしまいます。
2番に入った時には、ギターのカッティングがアルペジオに代わるとか、メロディに重ねてオブリガード(対旋律や合いの手)を入れて、さりげなく違いを見せることでまったく違う印象になることもあります。
作曲に使う楽器はピアノやギターPCソフト何でも良い

ピアノなどの鍵盤楽器でも、ギターなどの弦楽器でも、作曲の際に支障はありません。音階が出る楽器で、2つ以上の和音が奏でられれば作曲は十分可能です。
楽曲作成ツールをインストールしたパソコンでも問題ありません。
ツールを使い作曲をすると、バンド演奏までシミュレーションできるメリットもあります。
初心者におすすめのツール
・GarageBand(Mac)
・Zenbeats(Mac,Windows)
コードやメロディなどが思いつかないときの対処法

自分で作ったコード進行などを、日頃からストックしておくことは重要です。既存の曲のコード進行を調べて楽譜に残しておけば、勉強にもなるし作曲時に役に立ちます。コード進行のストックは作曲するための重要な財産です。
メロディは最初から狙って作れるものではありません。
なんでもない時に突然浮かんでくるものです。そんな時にはスマートホンなどに口ずさんで録音しておくと便利です。ヒット曲とまったく同じコードを、リズムやテンポを変えて演奏してみて、オリジナルメロディを考えるのも良い対処法です。
まとめ
メロディを考えるときは、まず音のリズムを決めてから音階をつけていく方法が良いと思います。歌のメロディを考えるなら、日本語特有の音のリズムと音階からイメージをふくらませていきましょう。気軽に口ずさむことから始めてみてください。
少し慣れてくると、コードを聴くだけでいろんなメロディが浮かぶようになります。たとえ未完成に終わっても、財産としてストックすることが、クリエイターへの近道といえるでしょう。