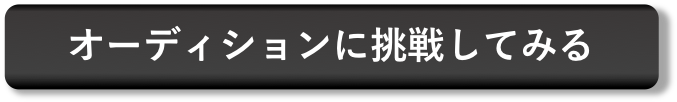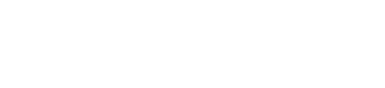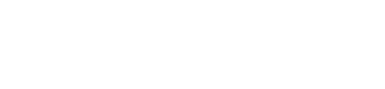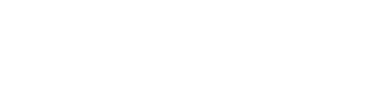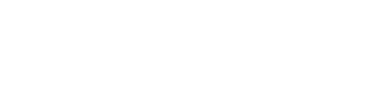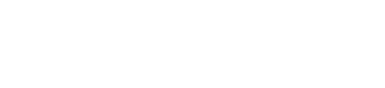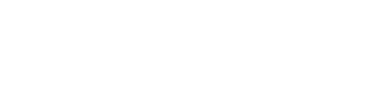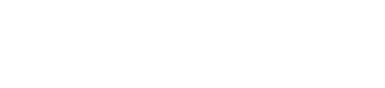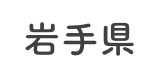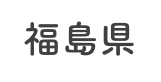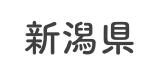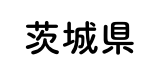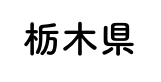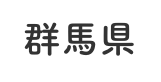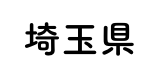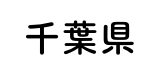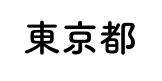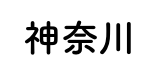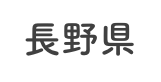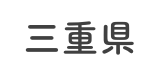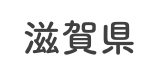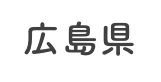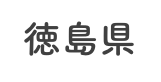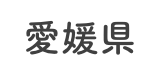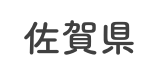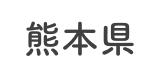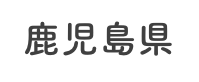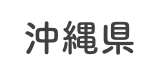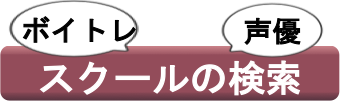スギやヒノキの花粉で毎年春になると、鼻づまりや喉がイガイガして思うように歌えない、声が出ないという悩みに直面している方は少なくありません。
花粉症ではないが鼻炎持ちだという方も含めると、多くの方が一度は鼻詰まりや喉のイガイガで歌えないという場面に直面しているのではないでしょうか。
今回は、そのような中でも「調子を整えて歌を歌いたい」というときに、筆者が(@ksm_c_emilyplay)お勧めしたい対処法についてご紹介します。
目次
大前提として専門医に診てもらい処方箋をもらう

当たり前のことかもしれませんが、花粉症やハウスダストなどによるアレルギー鼻炎や風邪などにより喉がイガイガする、鼻づまりがする場合は専門医に診てもらいあなたにあった薬を処方してもらいましょう。
中には、鼻の粘膜の炎症が鼻の奥にまでいってしまった場合、副鼻腔炎を患うといったケースもあるようです。
1日でも早く本調子で歌うためにも、医師から処方箋をもらうことを心がけてください。
加湿!とにかく加湿をする

喉がイガイガする、鼻詰まりがするときは加湿をしてください。
加湿器をつけたり、こまめに水を飲むなどです。
また、歌うとき以外はマスクをしたりマフラーをまいたりして乾燥を防ぐことも大切です。
空気が乾燥している状態は、喉や鼻の粘膜を作る機能が弱まるようです。
ただでさえ、喉や鼻が辛い状態なのに、乾燥した場所に身を置くことは自爆行為といっても過言ではありません。
加湿器などをつけて、湿度と温度が低い状態を避けることは、風邪などのウイルスが活発に動くのを沈めてくれます。
風邪や花粉で喉や鼻がやられている方も、お風呂に入っているときは症状がやわらいだりしますよね。
まずは、喉や鼻の違和感がやわらぐような空間作りから始めましょう。
食事にも注意を払い、万全の状態を目指す

体の内側からのアプローチも大切です。
お肉を摂取してたんぱく質を補い、柑橘類やほうれん草などビタミンが含まれている野菜を摂取して喉や鼻の粘膜の健康維持に配慮できるといいでしょう。
喉が痛い場合は、喉の痛みを沈めてくれる効果があると言われている「カモミールティ」や疲労回復の効果があると言われている「はちみつ」としょうがをお湯でといた飲み物などを飲むのがおすすめです。
鼻づまりが辛いときは、抗炎症作用があるといわれている大根やレンコンを積極的に摂るのがおすすめです。筆者も、鼻づまりがひどいときは大根をよく食べています。
鼻づまりの対処法

続いて、筆者も鼻づまりに悩まされたときにやっている具体的な対処法をご紹介します。
迎香と晴明のツボを押す

これは、ツボの本を読んで知ったのですが。(笑)
迎香(げいこう)と晴明(せいめい)というツボに人差し指の腹が当たるように指をおき、左右の人差し指で上下に軽くこすってください。筆者は20〜30秒ほどやっています。
また、軽くこすった後、それぞれのツボを軽く押してください。
鼻づまりが徐々にやわらいできます。
蒸しタオルなどで鼻を温める
粘膜の血流がよくなる、程よく湿気が得られるといったメリットがあり、鼻のとおりがよくなります!
ただし、一時的なものなので歌う時間の前に行うなどタイミングを見計らうことをおすすめします。
大根または蓮根おろしを鼻につける
大根おろし、または蓮根おろしをガーゼに浸したものを鼻の穴に入れる荒治療的な対処法です。
長い時間、鼻の穴の中にガーゼを入れたままだと筆者は痒くなってしまうため、数分だけ入れています。鼻の穴に入れるのに抵抗がある人は、鼻の穴の入り口にガーゼをあてるでもOKです。
喉のイガイガをどうにかしたいときは

喉がイガイガしている状態では、基本的に歌うことはもちろん、話すことも控えていただきたいというのが本音です。
しかし、そうもいっていられないということもあるかと思います。
そのようなときにおすすめしたい対処法をご紹介します。
それは、水溶性アズレンの喉スプレーをシュッシュッとすることです。
水溶性アズレンの喉スプレーは、ドラッグストアで800円程度の値段で購入できます。
水溶性アズレンは、カミツレという薬草の研究から得られた成分のようで、消炎作用と粘膜の再生・修復を促す効果があるといわれています。
ちなみに、カミツレという薬草はヨーロッパでは古くから民間薬として使われていたそうです。
水溶性アズレンのスプレーを喉に吹きかけるだけで、割とすぐに喉の不快感がとれるように思います。
ただし、1日に何回も吹きかけると、体に必要な常在菌までも殺してしまう可能性がありますので、ほどほどにしましょう。
筆者は喉がイガイガする日のみの使用を心がけ、使用する日は1日2〜3回にとどめています。
まとめ
花粉症やハウスダストなどのアレルギー鼻炎、風邪などにより喉のイガイガや鼻づまりがある中で、歌でできる限りのパフォーマンスを出すための対処法をご紹介しました。
筆者は医師ではないため、筆者自身がやっている方法をご紹介しています。
もし、対処に悩まれたときは専門医に診てもらい、あなたの状態に合った処方箋をもらってください。