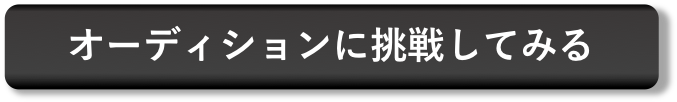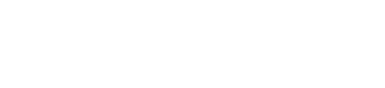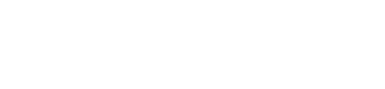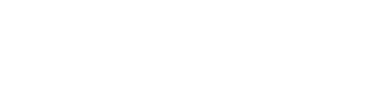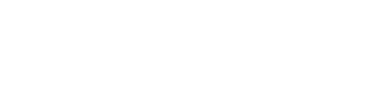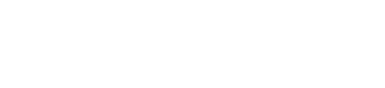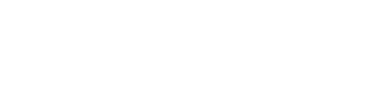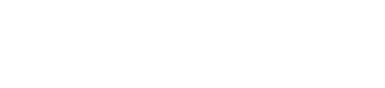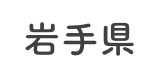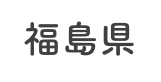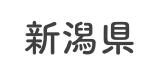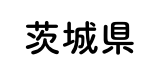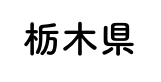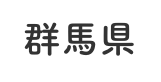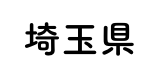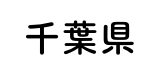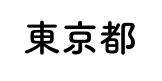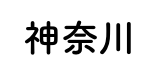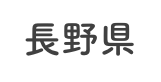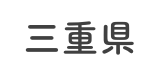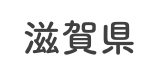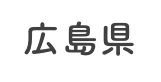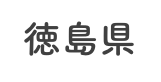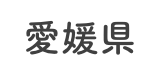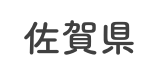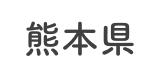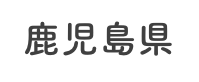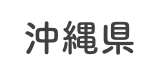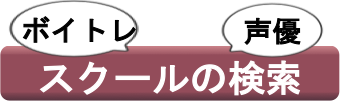今回は、音楽学校でどのようなことが学べるかについてご紹介します。
基本的には音楽系大学を想定してご紹介しています。
専門学校への進学を検討されている方は「進学を検討する方必見!音楽系専門学校で学べること」をご覧ください。
目次
演奏家

器楽、邦楽、演奏学、応用演奏学、ピアノ・オルガンなどが学べます。
器楽
管、打、弦楽器の中から自分の専攻楽器を決め、実技を中心に技術を極めます。
邦楽
三味線、長唄、箏、能楽などについてそれぞれ実技を中心に学びます。
演奏学
器楽と声楽を含めた内容をもち、実技を中心に学びます。
応用演奏学
電子鍵盤楽器について体系的なことを学びます。演奏、創作、理論の3分野が柱となります。
ピアノ・オルガン
高度な鍵盤音楽の研究、演奏を目指します。
声楽家
声の持ち味を生かしていくための技術を中心に声楽を学びます。声楽科といえどもある程度のピアノ演奏能力を求められます。
減点要素のない、欠点のない歌い方をすれば、抜群の成績で卒業できると言う方もいます。
学校の実技試験やコンクールの採点などは減点主義ですから、審査員になったつもりで、自分の演奏を聴き、評価できるようになると良いでしょう。
しかし、何のために自分は歌手になろうとしているのかを、真剣に考えなければいけません。
作詞・作曲家
作詞・作曲に関する技術、理論を身に付けるために、音楽理論・作曲法研究などを中心に、幅広い音楽講義と声楽・器楽の実技を学びます。
言語であれば、同じ発音と文法をもつ必要があるということになります。音楽の場合は、音階、和声、形式といった基礎条件がこれにあたり、作曲にまつわる理論的な面を学びます。
指揮者
オーケストラ指揮に必要な実技、スコアリーディング、幅広く深い楽器知識習得のための理論と実技が学べます。
例えば、音楽表現で一番大切なことのひとつにフレージングがあります。音符のどれとどれをつなげ、どこで切るのか、音楽に意味づけをする基本作業です。
これを間違えたら音楽の“意味”、つまり作曲者の真意が聞き手に伝わりません。ですから、スコアを開いて曲の勉強をするとき、その区切りをキチンと読解できるように、譜面の隅々まで目配りをして音符を読んでいかなければなりません。
指揮棒1本でどうやって100人のオーケストラに自分の意思=演奏意図を伝えるか、その技法を学びます。
学生にとっては、スコア・リーディング(譜読み)は生活の一部になるでしょう。また、オーケストラのピットの中では、楽員や伴奏者、歌手たちとのアイコンタクトが重要ですから、暗譜の仕方も学んでいきます。
音楽学

音楽学では、器楽、声楽、作曲、音楽などの専攻に分かれて学んでいきます。実技中心の場合と教養としての音楽学習に重点を置く場合があります。他にも、楽理、作曲理論学、宗教音楽学、音楽デザイン学などが学べる場合があります。
楽理
音楽の理論的な面を研究します。音楽史や作曲された時代背景などを分析する音楽分析などを中心に学びます。
作曲理論学
作曲・指揮、音楽学のそれぞれの専攻に分けられ、作曲にまつわる理論的な面を学びます。
宗教音楽学
作曲・指揮、音楽学のそれぞれの専攻に分けられ、作曲にまつわる理論的な面を学びます。
音楽デザイン学
コンピュータを利用した音楽・音響製作技術、音楽環境とのかかわり方などを研究します。
音楽教育学
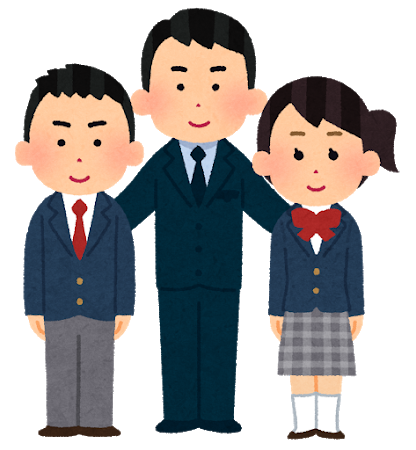
音楽教育学では、幼児から高校までの音楽教師を育てるために、音楽教育全般について研究します。学校教育ばかりでなく広い意味での音楽教育指導者を目指していきます。
他にも、音楽教育学の中で音楽制作における音響メディアに関する知識・技術や国や公共団体などの文化部門の担当者など、アート・マネジメントができる人材を育てる音楽技術運営学なども学べる場合があります。
まとめ
日本の場合、進学がその後の人生を決定する度合いが高いため、学校選びや受験は重大なターニングポイントで、過度に神経質になる傾向があるように思えます。
音楽学校で終了するものではなく、生涯に渡るものではないでしょうか。
例えば、学校を卒業してからも学習を継続することを、「生涯学習(life-long learning)」といい、「継続学習(continued learning)」という場合もあります。
音楽学校でできることは、時間的にも能力的にも限られています。20代ですべてのことをしようと思わない方が良いでしょう。18歳のとき音楽学校に進学できなかった人が、子育てや親の介護を終えて、40代、50代になってから音楽学校に入学するということも決して珍しくありません。
このようなことを「リカレント教育(recurrent education)」といいます。リカレントは再度「時流にあわせたものにする」という意味が含まれていて、「アップデート」することであり、ときに「回帰教育」や「還流教育」とも訳されています。
本記事を読んで、10年後、20年後の自分が音楽とどのように付き合っているのかを考えつつ、音楽系学校への進学を検討いただければ幸いです。